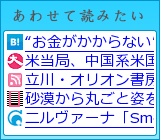« 2007年8月23日 | メイン | 2007年9月11日 »
2007年8月30日
■[リトルバスターズSS]それは円陣からはじまった(ネタバレ)
リトルバスターズ!の初SSを書きました。
時間軸としてはプレストーリーになりますか。物語の始まりに位置します。
物凄い全速力でネタバレですので、未プレイの方は御遠慮下さい。
個別シナリオのみクリアされた方もダメですよ。
タイトル画面の変化を御存知の方にお贈りします。
では、どうぞ。
ビーッ! ビーッ! ビーッ!
どこかで警報音が鳴り続けていた。
……真っ黒い世界に、わずかに赤い明滅が感じられた。
だが、他には何も見えない。暗い、漆黒の世界だった。
――どくん!
「……痛っ!」
突如、巨大な痛みの波に襲われた。まるで身体が浮き上がるような痛みだ。
――どくん!
右肩。
――どくん!
右肩が、酷く、痛い。
そして、そこから先の感覚が――なかった。
「!」
わたしは恐怖にかられて目をそちらに向けようとしたが、頭が何かにがっちりと挟まれているようで全く動かすことができなかった。
「これは、一体……」
それだけではない。湿った空気に濃密に漂う油のニオイ……。
そこかしこからうめき声が響いているのにも気付いた。
ビーッ! ビーッ! ビーッ!
どくん! どくん! どくん!
鼓動のたびに襲ってくる痛みの合間に、いくつかの笑顔が瞬いた。
――そして、脳裏に蘇る。
楽しい、楽しかったはずの、今日という日を。
――今朝。
教室に行くと、珍しい顔があった。
「あ。みおちんだ。おはよー!」
「……おはようございます」
葉留佳さんは他のクラスの人だが、彼女が必要以上にうちのクラスにいるのはいつものことなので別に不思議はない。
けれど、わたしよりも早く三枝さんが学校に来ているところは、初めて見た。
「いやもーなんだか暑いねー」
「夏も近いですから」
世間話をしていると、背後でがらり、と扉が開いた気配。
振り返ると、来ヶ谷さんが立っていた。
「おはよう。二人とも早いな」
「あっ姉御ー! いやいやー。はるちん、もう昨日から興奮しちゃって、朝5時には目が覚めちゃったのですヨ」
「おはようございます。……わたしは、いつも通りですよ」
「……と、言いつつ美魚君。髪の毛がはねているぞ」
「……!」
慌てて、指差されたあたりを手で押さえる。
――確かに、はねてるみたいだ。ぼっ、と顔が熱くなる。
……わたしらしくもない。
そういえば、今朝は鏡前に立った記憶がない。わたしも、はしゃいでいたのだろうか。……修学旅行に。
「はっはっはっ。美魚君のそういう顔は初めて見たな。早起きはするものだと思わないかね? 理樹君」
「……!!」
来ヶ谷さんの後ろから……本当に直枝さんが現れた。
「おはよう、西園さん」
「……は、はい」
……もう、消えてしまいたくなった。
「いや。理樹少年だけじゃないぞ。実は小毬君やクドリャフカ君とも校門で一緒になってな」
「おはようございますー! みなさんお早いですー」
ぴょこん、と、来ヶ谷さんの背中から能美さんの元気な笑顔が飛び出してきた。
続いてバタバタとした足音とともに小毬さんも登場した。
「……はあはあ。ふー。……みおちゃん、おーはよーう」
わたしの手に、小毬さんから何かが手渡された。
「濡れハンカチ……?」
「うん。よかったら使って?」
寝癖のことを再び意識して、顔が熱くなる。でも、小毬さんのいつもながらの邪気の全くない笑顔に、何も言えなくなってしまった。
……黙って、ご厚意に甘えることにする。
「うんうん。素直なのはいいことだと思うぞ、美魚くん」
来ヶ谷さんが何故か嬉しそうだ。
がらっ!
勢い良く開かれたドアに、再びみんなの視線が集中した。
肩で息をしていた女の子、鈴さんが顔を上げた。
「たいへんだ! バカとバカがまたバカをはじめた!」
「……ああ。真人少年と謙吾少年か」
苦笑めいた雰囲気が流れる。まあ、いつものこと、と言って良いと思う。
「して、鈴君。今度はいったい、何があったのかね?」
「……まあ、とにかく来てくれ!」
振り返りもせずに駆け出す鈴さんに、全員がついてきた。
……あいかわらず、みんな付き合いが良い。
……あ、わたしもか。
校門脇の木立、その物陰にずんずんと荷物が積みあがっていた。
「理樹、早く止めてくれ! やつら、絶対くちゃくちゃロクでもないことを始める気だ! 修学旅行がくちゃくちゃ旅行になるぞ!」
鈴さんにせかされ、直枝さんが素朴な疑問を一息ついていた宮沢さんに投げかけた。
「……何してるの? 二人とも」
「ん? ……いや、その、恭介に頼まれてな」
「よっ、せっと……。これで全部か」
重そうに井ノ原さんが下ろしたものは……巨大なクーラーボックスだった。しかも、井ノ原さんの足元にもう一つある。都合二つ。
他にも、小型バッテリーに扇風機。用途は分からないけれど何種類かのケーブル類。恐らくひまつぶし用の漫画類。
そして、うず高く詰みあがった、色とりどりのクッション。
……まあなんというか。
これは、どう見ても。
「……来る気だね、恭介」
おかしくてならない、といった様子の直枝さんに、来ヶ谷さんがにやりと応じた。
「……ああ。全く恭介氏にも困ったものだ」
袖で汗を拭きながら、井ノ原さんが宮沢さんに問いかける。
「で、どうすんだ? あいつ荷物室にでも忍び込む気か?」
「多分、そうなんだろうな……」
「……ええっ! それは、いくら恭介さんでもムチャだと思いますっ!」
能美さんが常識的な心配の声をあげたけれど。
「まあ、でも恭介だしな」
という、井ノ原さんの一言にわたしたち全員の心境は集約されていた。
恭介さんはどうにかして忍び込んで、どうにかして修学旅行について来るのだろう。
そしてわたしは、またリトルバスターズの誰かが巻き起こした、わけのわからないことにわけのわからないままに巻き込まれて、そして……楽しい旅行になるのだろう。
小学校中学校と、わたしにとってわずらわしいばかりだった修学旅行という行事が、まるで違った意味を持つようになるのだろう。
そうなるはず、だった。
……のに。
目を開く。
明滅。
あかい、くろいせかい。
あの警報音が聞こえる。
でも、何故かひどく遠い。
だんだん、意識が朦朧としてきた。
肩を乱暴に襲い続ける痛みですら、わたしを現実に繋ぎとめてはくれないようだ。
すっ……と、意識がまっくろになろうとした、その瞬間。
『誰か! 誰でもいい! 鈴を……理樹を、助けてくれ!』
酷く聞きなれた、けれど酷く違和感のある声だった。
誰の声だろう。
『たのむ――だれか――どうか、りんとりきを、たすける……ちから……を……』
ついに、その声は涙を流しはじめた。
涙は波紋となって、バス全体をつつんだ。
……その時、ぼんやりしていたイメージが眼前で明確な像を結んだ。
恭介さんが泣いていた。
泣く筈のない人が泣いていた。
直枝さんと……鈴さんをたすけてほしいと、わたしたちのリーダーが泣いていた。
状況は良くわからない。
けれど、否やはなかった。
わたしは、ふらふらと手を伸ばし、さまよっている恭介さんの手をぎゅっと掴んでいた。
気がつくと、わたしは白い世界に横たわっていた。
周囲を見渡したが、深い霧に阻まれて何も見渡すことができない。
それでも目を凝らすと、建物のシルエットがかろうじて確認できた。
慣れ親しんだシルエット。
――学校。
ここは多分、わたしたちの学校の、それも中庭だ。
ただ、何故だかやたらと霧が深い。
……でも、学校?
今日は修学旅行で、わたしたちはバスに乗って、それで……。
「西園。気がついたか?」
不意に、聞き慣れた声がした。
「……恭介さん、ですか?」
「ああ」
恭介さんは、難しい顔をしてこちらを見下ろしていた。良く見ると、恭介さんの両脇には、井ノ原さんと宮沢さんの姿もあった。
周囲には、他のリトルバスターズのメンバーが、眠るように横たわっていた。
「……ここは、一体」
「西園は、あっちで意識を取り戻したか?」
「……あっち、ですか?」
記憶が蘇る。――明滅するイメージ。経験したことのないほどの痛み。
こくり、と頷いていた。
「そうか……」
「……んー」
「あれ? ここどこ? バスは?」
「……」
「……ん? なんだ、ここは?」
「むにゃむにゃ……もう旅館についたですかー?」
もぞもぞと、他のメンバーも目を覚ましはじめた。皆不思議そうにきょろきょろとあたりを見渡している。
「……あれ? 直枝さんは?」
そこで気付いた。人数が足りない。
よく見ると鈴さんの姿もなかった。
とにかく状況が全くわからない。わたしたちの視線は、自然に沈黙を守っている恭介さんのところにあつまっていた。
「――正直、俺にも正確な状況はつかめない」
問わず語りに、恭介さんが語り始めた。
「わかっていることは、ここが普通の世界ではなく、俺たちの意識が作り出した世界だということだ」
「……え?」
「ど、どういうことですか?」
小毬さんと能美さんが疑問の声をあげる。それは、わたしたち全員の疑問だった。
「言葉どおりさ。たとえば……」
恭介さんが握っていた手を開く。すると、そこにポンと綺麗な花が咲いた。
「ふえっ?!」
「……どういうことだ、恭介氏」
「みんなはバス事故のことは覚えているか」
「……」
その一言に、水を打ったようにしんと静まり返る。
「……やはり、あれは本当にあったことなのだな?」
来ヶ谷さんが冷静に確認した。
「そうだ。そして、俺たちは現在瀕死の状態にある。……残念ながら俺たちが助かる可能性は非常に低い。……バスの燃料が漏れ出しているんだ」
ひっ! と、能美さんが息を呑んだ。
「……幸い、理樹と鈴は、真人と謙吾がとっさにかばってくれたお陰で、大した外傷がない状態だ」
ほっとした空気が流れた。……わたしも、ちょっと涙が出そうになった。
「俺は、俺たち全員を失った後の世界でも、理樹と鈴が幸せに暮らしてくれること。それを強く望んだ。でも今の二人は、弱い。……これはとても、実現が難しい願いだ」
「……」
「俺は必死で叫んだ。誰か、どうか助けてくれと。……そして、気がついたらここにいたんだ」
そこで、恭介さんは自分の手をじっと見つめ、ゆっくりと開いたり、閉じたりしていた。まるで何かの感触を確かめるように。
自分の手をみつめる。恭介さんの手をとった温もりを思い出した。
気付くと、全員がわたしと同じように自分の手をみつめていた。
……そうか。みんなそうだったんだ。
こんな状況なのに、わたしは嬉しくて泣きたくなってしまった。
「俺は、俺たち三人は決めた。この事故で理樹と鈴は俺たちを失うことになる。その先の世界にあいつら二人が踏み出せるように、そのためにこの最後の時間を使おうと」
そういって恭介さんは、拳をぐっと突き出した。
その拳に、無言で井ノ原さんと宮沢さんが、ぐっと手のひらを重ねた。
「難しいことはわからねえ。でも俺は、これが最後だってんなら、理樹と鈴のためにできるだけのことをしてえんだ」
「……完全に同意だ。真人とここまで意見があうなんてな」
そして、二人はにっと笑った。
「そうして作ったのがこの世界だ。……正直俺たちには絵心がなくてな。校舎の再現度はイマイチだ。だから霧でごまかしている」
恭介さんは苦笑をうかべた。
……なるほど。
「できれば、みんなの力をかしてほしい。……何の得にもならない話だ。むしろマイナスかもしれん。だから、これはただの……お願いだ」
――わたしの答えは決まっていた。
「要するに、こういう感じでお手伝いすればいいんですね?」
手のひらを中心に円陣を組む三人の手の上に自分のてのひらを乗せ、強くイメージする。
わたしがみんなに……直枝さんに出会って、一人でなくなった場所。一人でなくなってしまった場所。
――たぶん、もう帰れない、あの場所を。
「うおっ! こりゃ何だあ!?」
「わあ! すごいですっ!」
「すげー! みおちんすげー!」
上がった歓声に目を開くと、わたしが思い描いた通りの校舎が、中庭が、空が……世界がそこに広がっていた。
「すごいな。こりゃもう本物と見分けがつかないぞ」
普段沈着冷静な宮沢さんまで、ちょっと興奮しているみたいだ。
わたしは少しだけ調子に乗って言ってみた。
「……他の事ではみなさんに敵いませんけど、妄想力なら誰にも負けません」
「ははっ。さすがだな!」
恭介さんが空いているほうの手でわたしの肩をたたく。
役に立てたのが嬉しかった。……ちょっと痛かったけど。
「なーるーほーどー。じゃあ私は」
そう言いながら、小毬さんがわたしの手の上に手のひらを重ねた。その手にぐっと力がこもる。
降り注ぐ光に微妙な変化を感じて、皆で空を見上げた。
「空が――」
単調だった空の色が変わっていた。
ただ蒼いだけでない空。
ただ白いだけでない雲。
見せられてみると、確かに空というのはこうでなければいけない。
「あとね。この学校は夜空が綺麗なんだよー? 知ってた?」
小毬さんが右手の人差し指をぴんと立て、くるりと回すと、一瞬にして世界が暗転した。
「わふっ!」
「うわ!」
目が慣れてくると、空に銀の輝きがいくつも瞬いているのが見えてきた。
「あっ。流れ星!」
「これは風情があるな」
「……みんな、見えた? じゃあきっとみんなの願いは叶うよ」
にっこり笑って空を青空に戻しながら、小毬さんは言った。
「じゃあねえ、次ははるちんに任せてもらいましょーか!」
手に、三枝さんの重みを感じると、中庭にベンチや花壇の柵、「花を大切に」のたて看板などが追加された。
「こういう備品なんかも、リアリティの上では重要なのですヨ?」
「私にもお手伝いさせてくださいっ!」
能美さんも輪に飛び込んできた。
能美さんにはちょっと手の位置が高すぎたので、みんなで下げると、満面の笑みで能美さんが手を添えた。
――小鳥が、蝶が、蜂が、蟻が。にわかに世界はにぎやかになった。
輪に一人加わるたびに、真白かった世界に、新たに一筆ずつ入っていくようだった。
「……理樹少年を大人にしてしまうのは個人的に非常に残念だが……少年を無理やり大人にするという趣旨には、ちょっと惹かれるな」
最後に、来ヶ谷さんが手を乗せると、唐突に旧校舎が登場した。
「あ、いけね。そういうのもあったな!」
井ノ原さんが感嘆の声を上げた。
「立ち入り禁止ですから、忘れてましたっ」
「……ちなみに、旧校舎内もちゃんと知ってるからな。中にも入れるぞ」
得意げに補足する来ヶ谷さん。
――わたしは、思いあがりを恥じていた。
わたしが知っている学校なんて、まだまだ狭かった。味気なかった。
改めて、みんなで作った世界を見渡して思う。確かにこここそが、わたしの、わたしたちの、学校だと。
そうして一人ずつ加わり、自然に組みあがった円陣。
その中心で、恭介さんは言った。
「――ありがとう。みんなのおかげで、この場所は理樹と鈴を迎え、鍛え上げるのに最適な場所となった」
――泣きそうな恭介さん。でも、さっきとは違う。
今の恭介さんは嬉しそうだった。
わたしは思い出していた。みんなもそうだと思う。
あの、ぼろぼろに負けた野球の試合の日のことを。
あの日も、この円陣で始まった。
「これより、リトルバスターズのラストミッションを開始する。しまっていくぞ!」
「応っ!」
みんなの声が、一つに聞こえた。
【このエントリにはタグがつけられていません】
投稿者 文月そら : 03:00 | コメント (4) | トラックバック